ニュース&トピックス
News
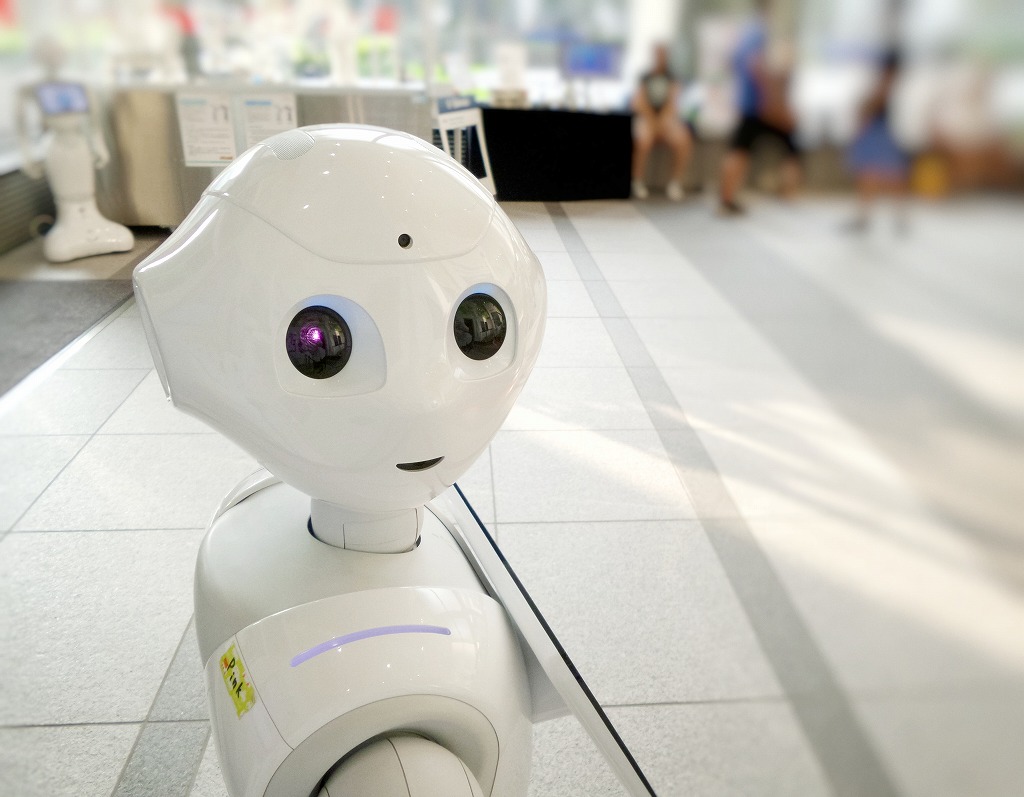
2019. 12. 16
学園長コラム【学園長コラム vol.18】金持ちを目指せ
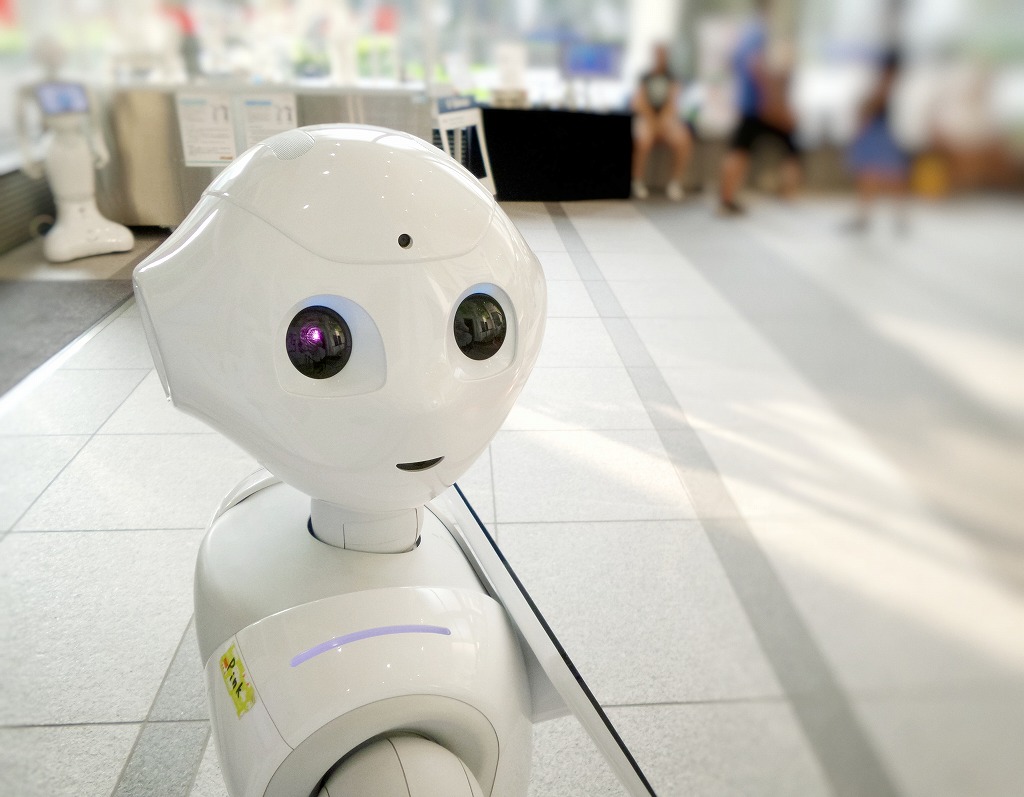
日本の小説やドラマ、古い映画によくある設定で、由緒ある名家の美しい令嬢が、
一代で成り上がった金満実業家のもとへ嫁入りする。
名家を存続させるためのカネ目的の結婚であり、
ストーリーは令嬢を悲劇のヒロインとして描き、
成り上がり者をエネルギッシュだが油ギッシュの「すけべオヤジ」として描く。
この感覚、この文化が日本のITにとっての大きな欠点だ。
日本では「一代で経済的に成り上がった者」を、成り上がり者と呼ぶが、
米国ではこれをサクセス・ストーリーと呼ぶ。
日本では千年前に成り上がった者の子孫が次第に地位や富を失って行く姿を、
没落貴族などと呼びつつも名家だ歴史だと言って尊重するが、米国の歴史はまだ300年もなく、
親や祖先の資産を食い潰すバカ息子やバカ娘は映画では極めつきのバカとして描かれる。
米国で発明、開発された多くの技術は、自動車、家電、コンピュータメモリなど
いずれも日本に導入されて米国を追い越す進歩を見せてきたにもかかわらず、ITだけはそうではない。
ITは技術だけではない、金儲けに対する知恵と意欲がなければ大発展はしないのだ。
日本では、「金儲けにはならないが、社会のためになる」ことをしている人が一番人気で、
「金儲け」している人に対しては、「なんか怪しい」とか勘ぐったりすることが多い。
TVニュースで流れるAI人口知能の事例は、レントゲン写真をAIに学ばせ、
肺がんなどの異常を発見するものが中心で、これを歓迎する視聴者であっても、
AI活用中の病院にその分だけ余計な金額を払おうとはしない。
「国が払うべき」とか言って、結局全員が税金で払う額を増やすのだ。
つまり、誰も反対しないが、誰もカネを出さない事例を奨励し、税金でやるべしと言い、
ただし私の税金は上げないで、これが日本人。勝てるわけがない。
Amazonは最初、ネット本屋だった。
しかしこのときから既に同社のロゴマークはaとzの下をカーブの下線で結び、
「aからzまで」つまり、何もかも扱うという意欲を見せていた。
「何もかも扱う」ことが書籍販売にも効果をもたらし、勝利へ導くと信じたからだろう。
ではなぜ、最初に本を選んだのか。
「何もかも」が本当に最高収益をもたらすのか。
世界中の「何もかも」に頼んでいたら間に合わない、
逆に先方から「アマゾンで売ってくれ」と頼みに来るように仕向けなければいけないが、
大成功する以前の段階ではどんな戦術でそれを実現したのか。
「客が増える」と「商品が増える」と「出展者が増える」の3つを好循環で回すには、
どれをトリガーとして動くのが良いのか、それは状況によって変化するのか。
ITは儲かります。
誰もが使いたい、カネを払ってでも利用したいと思うことを実現できれば。
そしてそれには技術だけではないセンスが必要だ。
そういう才能を多大な努力で伸ばし、金持ちになった者を尊敬するようになれば、
日本が勝てる可能性が出てくる。

ITカレッジ学園長 佐藤 治夫
<プロフィール>
東京工業大学理学部数学科卒業。
ITエンジニアとしてコンビニ、アパレル、保険、銀行、人材派遣など様々な業界のシステム開発を手がけ、現在は株式会社クレスコ社外取締役、ユーザー系企業・顧問 情報活用コンサルティング、IT系企業・顧問 事業戦略策定コンサルティングを兼務。「ダメなシステム屋にだまされるな」(2009年日系BP)など、IT関連の著書も多数。
▼バックナンバーはこちら▼
【学園長コラム vol.1】毎日の仕事はITだらけ
【学園長コラム vol.2】プログラミングの初仕事
【学園長コラム vol.3】世界を変えるためにやっている
【学園長コラム vol.4】異常終了 - アベンド -
【学園長コラム vol.5】天才ユーザー(アパレル)
【学園長コラム vol.6】等比数列の和の公式
【学園長コラム vol.7】業種とIT
【学園長コラム vol.8】世界のIT
【学園長コラム vol.9】Win - Win - Win
【学園長コラム vol.10】Why don't you come to me?
【学園長コラム vol.11】経済産業省が鳴らす警鐘
【学園長コラム vol.12】AIとIoT
【学園長コラム vol.13】天才ユーザー(コンビニ)月曜夜9時の少年ジャンプ
【学園長コラム vol.14】天才ユーザー(百貨店)
【学園長コラム vol.15】メガ、ギガ、テラ
【学園長コラム vol.16】バッチ処理
【学園長コラム vol.17】恐怖の無限ループ