ニュース&トピックス
News
2019. 10. 28
学園長コラム【学園長コラム vol.11】経済産業省が鳴らす警鐘
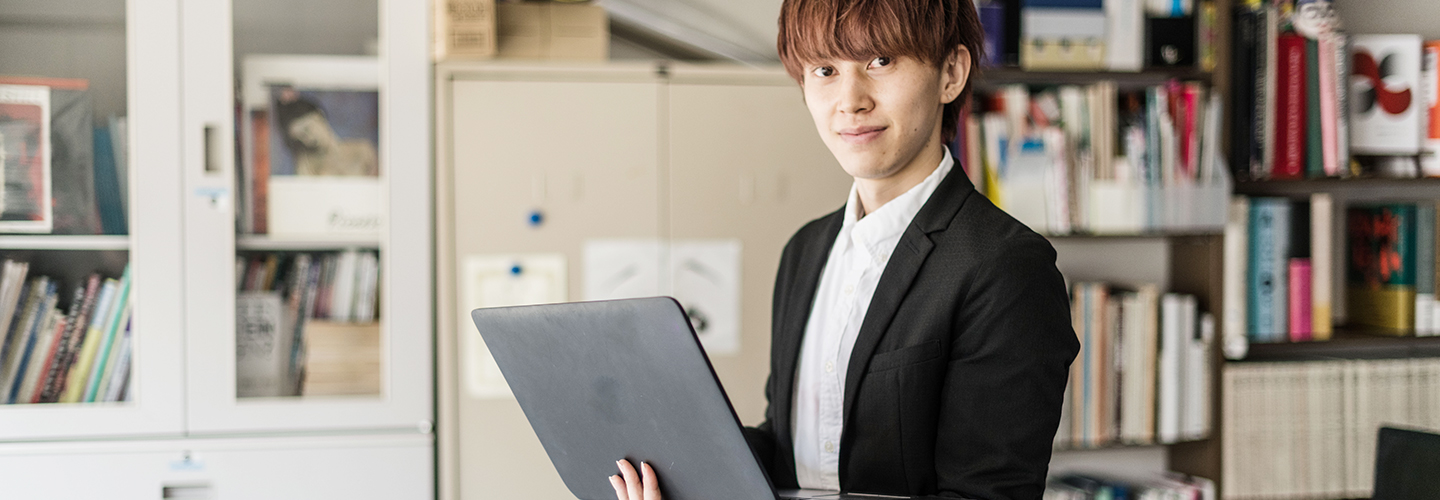
2019年4月に経済産業省が発表した「IT人材需要に関する調査」によると、
2030年には、「従来型IT人材」が10万人余剰となり、
一方、AIやIoTなどを活用する「先端IT人材」は55万人不足する、となっている。
「AIやIoTに注力する当学園の生徒は、だから安心してください」
などと単純なことを言うつもりはありません。
最初に、経済産業省が鳴らす警鐘とはどういうものか、を考えてみよう。
かつて「日本人の全員がプログラマになってもまだ不足」という警鐘で悪名をはせた経済産業省だ。
懲りずに同種のことを言うのは何のためだろうか。
第二次世界大戦の戦前、「軽工業から重化学工業へ」と謳い、
戦後は自動車産業やコンピュータ製造業の発展を牽引した彼らは、
次に何に注力しないと世界における日本の相対的地位が低下する
という危機意識を常に持っている。
だから、参考にはなる。
一方、従来型IT人材は余剰、すなわち生き残れないという主張は何をねらったものなのか。
私がこの世界に入って40年間、何度か大きな技術革新があり、革命と呼べるようなうねりさえあった。
私が最初に経験したのは、大型コンピュータの性能が飛躍的に向上した1970年代、
それまでコンピュータの処理効率優先でソフトウェアを開発してきたが、
むしろソフトウェア開発や修正の生産性向上が優先課題となり、
標準化を中心とした生産技術革新があった。
このときも従来型のやり方は通用しないと言われた。
次に1980年代後半、小型のワークステーションが急拡大し、
その基本ソフトウェアOSはUnix、そしてプログラミングはC言語が主流となったときも
従来型人材は生き残れないと言われた。
1990年代後半、PCが主流となりインターネット利用が当たり前となったときも、
従来型人材には出番がないと言われた。
40年間、どの局面でも「従来型IT人材」であった私は、なんとか生き延びている。
そして私の感想だが、従来型で優秀であった人たちもやっぱり生き残っている。
技術革新に終わりはなく、10年から15年に一度ぐらいの頻度で、
それまで想像できなかった世界が突如として現れてきた。
しかし、常に変わらないのは、ITを利用するのは人間であり、企業などの組織であり、社会であるという真理だ。
何に価値があるか、どうすればよりよい社会、より面白い展開が実現できるかを考え続けていれば、
新技術に対して恐れることなく柔軟に取り組むことができるものだ。
私が保証する。

ITカレッジ学園長 佐藤 治夫
<プロフィール>
東京工業大学理学部数学科卒業。
ITエンジニアとしてコンビニ、アパレル、保険、銀行、人材派遣など様々な業界のシステム開発を手がけ、現在は株式会社クレスコ社外取締役、ユーザー系企業・顧問 情報活用コンサルティング、IT系企業・顧問 事業戦略策定コンサルティングを兼務。「ダメなシステム屋にだまされるな」(2009年日系BP)など、IT関連の著書も多数。
▼バックナンバーはこちら▼
【学園長コラム vol.1】毎日の仕事はITだらけ
【学園長コラム vol.2】プログラミングの初仕事
【学園長コラム vol.3】世界を変えるためにやっている
【学園長コラム vol.4】異常終了 - アベンド -
【学園長コラム vol.5】天才ユーザー(アパレル)
【学園長コラム vol.6】等比数列の和の公式
【学園長コラム vol.7】業種とIT
【学園長コラム vol.8】世界のIT
【学園長コラム vol.9】Win - Win - Win
【学園長コラム vol.10】Why don't you come to me?