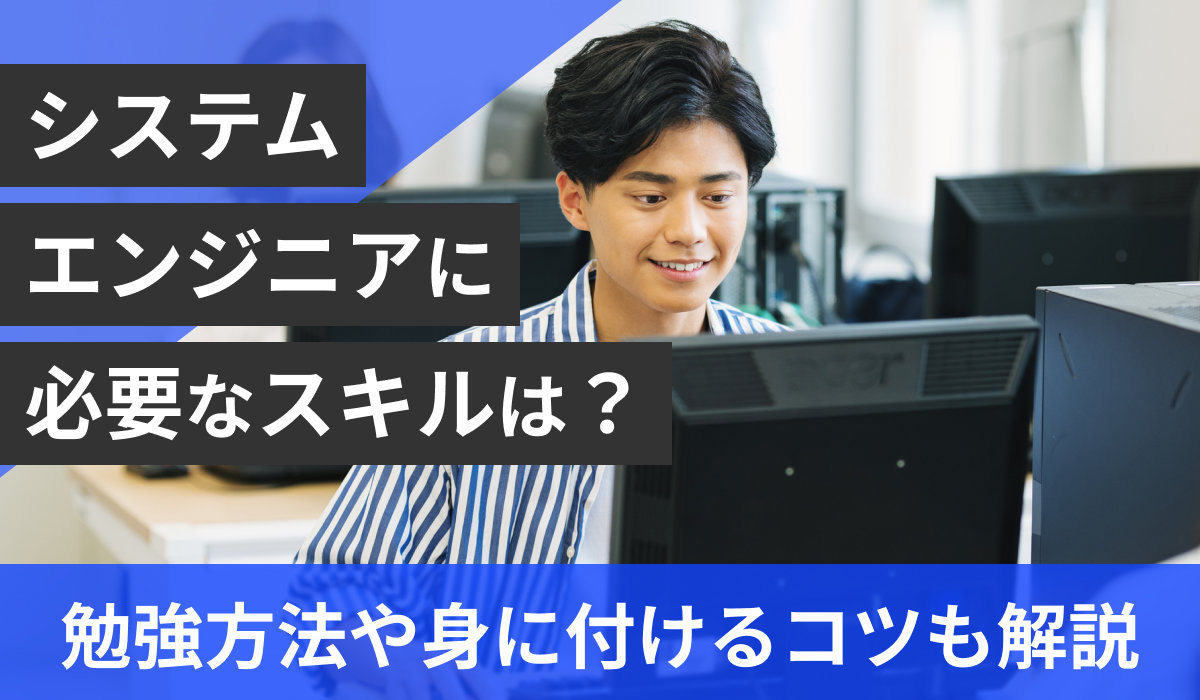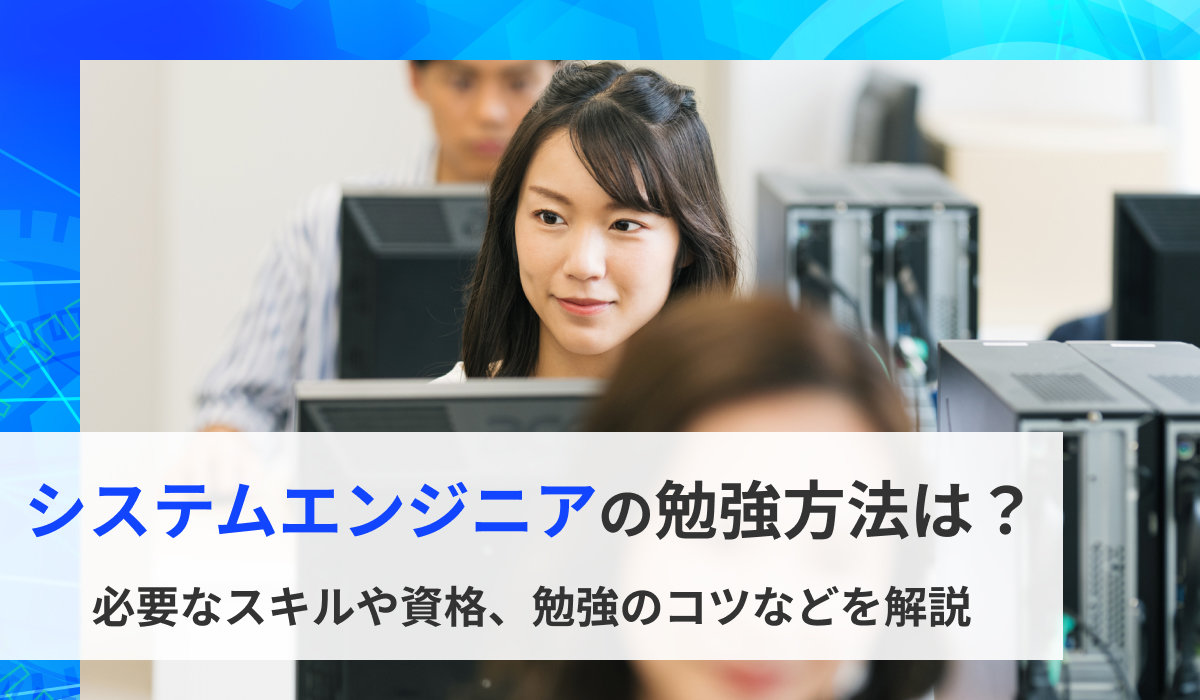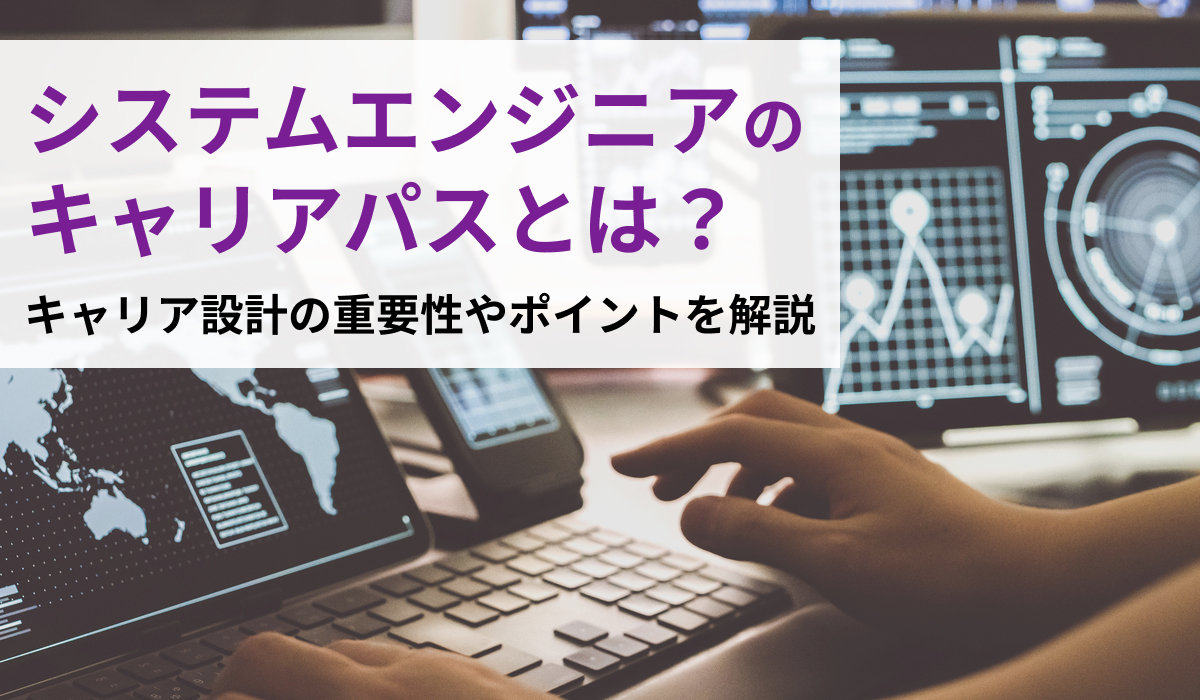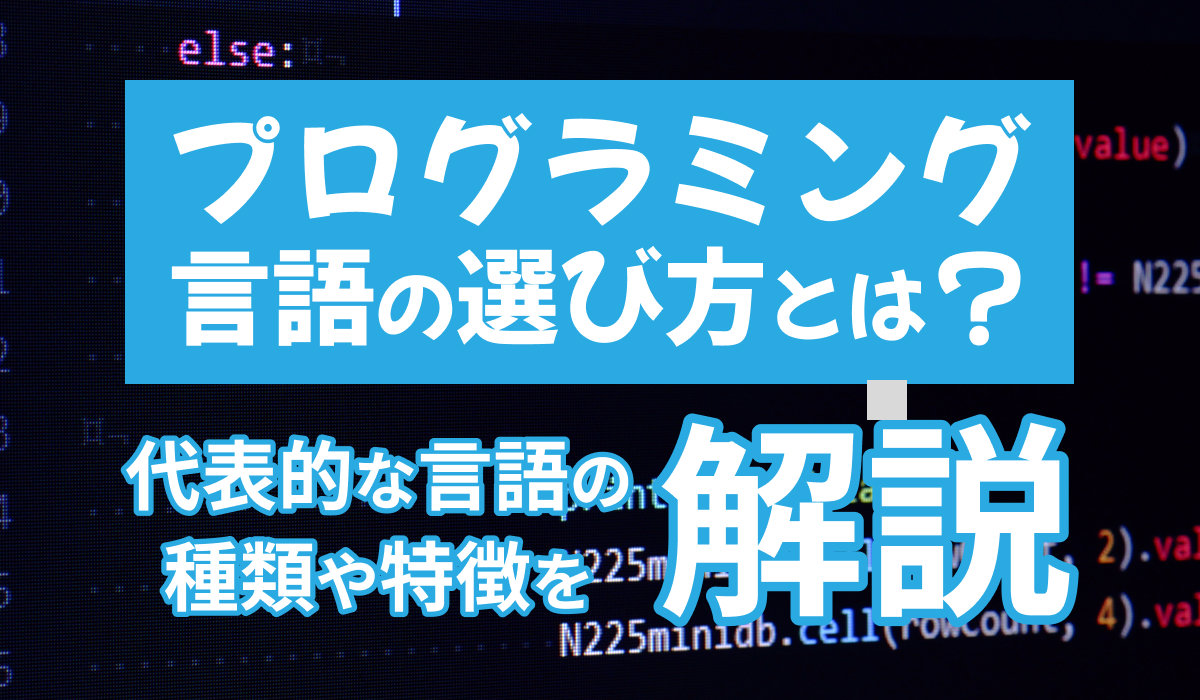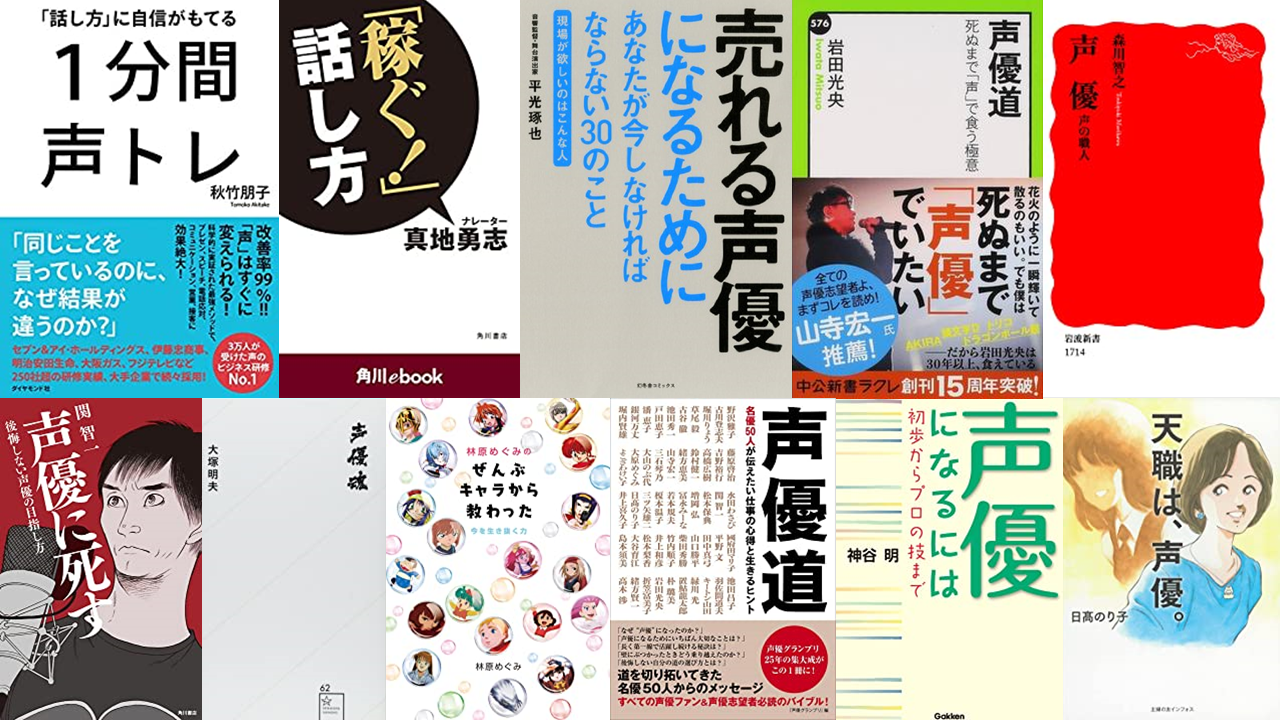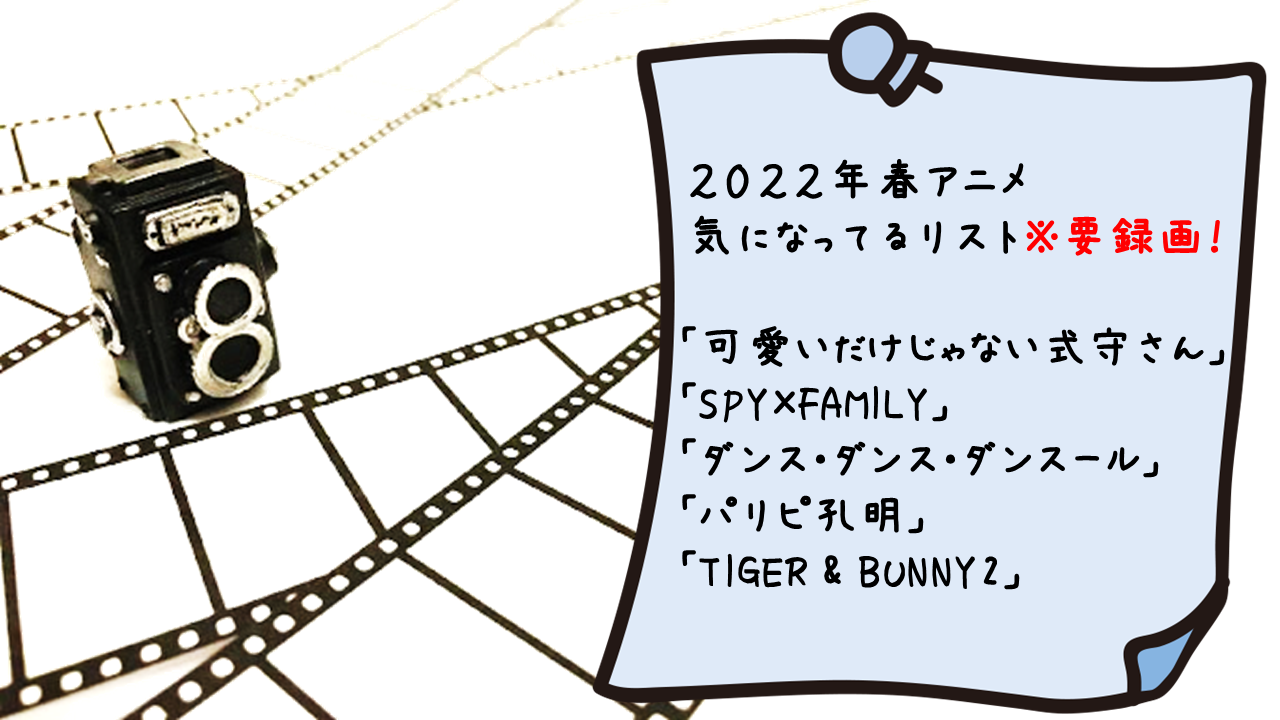IT
ITエンジニアになりたい!専門学校と大学どっちを選ぶべき?
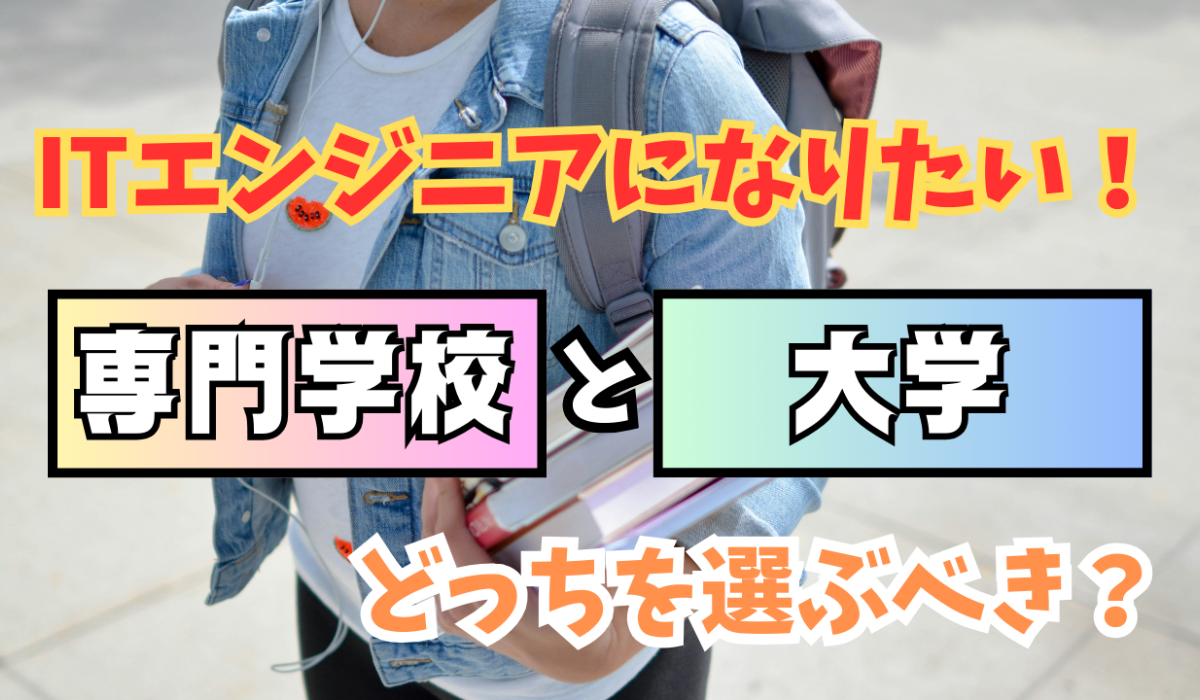 将来ITエンジニアを目指したいけれど、専門学校と大学どっちを選ぶべきか悩んでいるという人も多いでしょう。
将来ITエンジニアを目指したいけれど、専門学校と大学どっちを選ぶべきか悩んでいるという人も多いでしょう。
本記事ではITエンジニアを目指すにあたって、専門学校と大学それぞれを選んだ場合のメリットやデメリット、どんな人がどちらへの進学がおすすめなのかといった、進学先選択の指針を解説します。ぜひ参考にしてみてください。
【目次】
専門学校で学ぶメリット・デメリット
IT企業への就職を目指すにあたって、専門学校と大学のどちらを選んだ場合でも、それぞれメリットとデメリットが存在しています。まずは専門学校を選択した場合のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
①専門的な知識を学べる
専門学校は名前のとおり専門的な知識を学ぶための学校です。
ひと口にITエンジニアといっても、各種アプリケーションやゲームなどを開発するプログラマー、システムの設計・開発・管理を行うシステムエンジニア、近年注目を浴びるAI関連の開発やデータ分析を行うAIエンジニアなどさまざまな職種があり、必要とされる知識も一部重複こそあるものの、それぞれ異なります。
専門学校ではそれぞれの現場で必要とされる知識を専門に学べるほか、各種課題をとおし実際に手を動かして実践的なテクニックを身に着けることが可能です。
②必要な資格を効率よく取得できる
選択した学校やコースなどによっても異なりますが、専門学校のカリキュラム自体に資格取得のための対策や準備が含まれていることが多いです。
就職時や実務で求められる専門資格を、短期間で確実に取得できるのは見逃せないメリットといえるでしょう。
③早く働き始められる
大学が4年制なのに対してIT系の専門学校は2~3年制のものが多いため、大学に比べて早く卒業でき大学に進学した場合よりも早く働き始めることができます。
また、専門の人材を育成しているため、専門学校と企業間のつながりを利用して、条件にマッチした就職先を紹介してもらえる点もメリットといえるでしょう。
④専門学校のデメリット
専門学校を選択した場合のデメリットについても考えてみましょう。
専門学校では実務に即した知識を学ぶ関係上、卒業後に大幅に進路を変更することは難しくなります。とくにITと無関係の職種に進むといったことは難しくなるでしょう。
参考までにヒューマンアカデミーのような専門校の場合、通常の専門学校と違いほかの専攻を同時に学習できる「クロスオーバーカリキュラム」があるため、進路の変更も不可能ではありません。
また大学と比較して、学歴面や収入面で不利になる可能性があります。企業の中には大卒を条件とする企業も存在しますし、より現場に近い部署での採用が多くなる分、給与の面でもやや不利になる傾向があります。
ただしITエンジニアは就職先で実績や経験を積んでスキルを磨き、能力給のアップを目指したり、より条件のよい企業に転職を繰り返してキャリアアップを図るのが当たり前の業界なので、他業種に比べ最終学歴のハンデを覆しやすいとも言えます。
さらにヒューマンアカデミーの場合、大卒が条件の企業にも合格した実績もあるほか、並行して大学に通ったり、大学に編入する制度も用意されているので、大学と迷っている方は、併願受験なども検討してみるのもよいでしょう。
大学で学ぶメリット・デメリット
専門学校のメリット・デメリットに続けて、今度は大学を選択した場合のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
①幅広い知識を学べる
大学では広範な知識と教養を学べるのが最大のメリットといえるでしょう。語学や数学といった一般教養科目も学べるほか、IT分野においても電気回路やコンピューター、情報処理の理論や仕組みなどを学問として体系的に学ぶことができます。
教養の価値は見えにくいものですが、年齢を重ねたり社会的地位が上がったときに、人間としての価値を高めてくれます。
広範な知識を学ぶため、卒業後の進路に修正が利きやすい点もメリットといえるでしょう。
②大卒の学歴を得られる
実利的な面でいえば、大卒の学歴が得られるのが大学を選ぶ最大のメリットかもしれません。
IT系の分野においても、就職の条件として大卒が求められる企業が存在しています。就職において大卒が有利であるのは間違いないでしょう。
また、大卒者は管理人材とみなされるケースが多く、初任給の面では大学が有利と言えます。ただし、その後は管理職としてのキャリアを歩むことが多いため、もし直接的に実務に特化した仕事を希望するのであれば、専門の学校に進学し、能力給での昇給を目指すという選択肢も考えられます。
③コミュニケーション能力や人脈を築ける
大学には広い地域から多くの人が集まりますし、まったく異なる分野の人とも一般教養課程やサークル活動を通じて交流を図るチャンスもあります。
大学で得た幅広い人脈が、思わぬチャンスにつながるといったことも少なくありません。
ITというとパソコン相手の個人作業と考えてしまいがちですが、開発時に仕様を決定するにあたって、さまざまな人たちと意思疎通を図る必要がありコミュニケーション能力が求められる場面も数多く存在します。大学での幅広い人材との交流は無駄にはならないでしょう。
④大学のデメリット
大学を選択した場合のデメリットについても考えてみましょう。
まず考えられるのが、卒業に4年と比較的長い期間と費用がかかることがあげられます。時間的な余裕があるともいえますが、4年間のお金を工面するのが難しい場合や、早く働き始めたいという人にとってはデメリットといえるでしょう。
また、専門学校の1年目にかかる学費の平均額が約121.4万円なのに対して、大学の平均額は約148万円高めなこともデメリットといえるでしょう。4年制の専門学校以外と比較すると、その差はより開くことになります。以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
・エンジニアになるには?専門学校の学費相場やメリット・デメリットを解説
https://ha.athuman.com/humanstar/blog/it/post_222.html
さらに自由度が高く幅広い知識が学べるという大学の長所は、裏を返せばしっかりとした目的意識を持っていないと必要な知識を学ばずに卒業してしまうことにもなりかねません。
現場で使われているテクニックを学ぶというより、基礎的な理論を学ぶ傾向が強いため、卒業後に実務経験の中でテクニックを磨いていく必要もあるでしょう。
どっちが自分に向いているのか考えてみよう
専門の学校と大学、それぞれのメリットとデメリットを把握したところで、次はそれぞれがどんな人におすすめかを考えてみましょう。
①こんな人には専門の学校がおすすめ
専門の学校がおすすめなのは、何といっても早く働き始めたい人です。比較的短い在学期間で済ませられますし、学費を抑えることができます。早く働き始めることは実績や経験をいち早く積むことにもつながるでしょう。
次に就きたい職業のビジョンが明確な人にも専門の学校がおすすめといえます。たとえばゲームプログラマーを目指したいのであれば、専門コースを選択することで、直接関係のない講義に時間を割かずに済み、業務に必要な技術やテクニックを効率よく学ぶことができます。
②こんな人には大学がおすすめ
大学がおすすめなのは、まず広範な知識を学びたい人があげられるでしょう。教養を身に付けられるだけでなく、一見関係ないような知識であっても意外なところで役に立つことも珍しくありません。
また将来IT業界に進みたいと思っていても、具体的なイメージが固まっていないという人にも大学がおすすめと言えます。
4年間という長い在学期間を利用してより興味を持てる分野を探せます。在学中に興味の方向が変わってしまったという場合でも、軌道修正が容易ですし、一般教養課程を修めたうえで別の学科に転科するといった手段も利用できます。
決めかねているならオープンキャンパスを体験してみよう
この記事でITエンジニアを目指すために自分が専門の学校と大学のどちらを選ぶべきか、ある程度の指針が得られたのではないでしょうか。
もしそれでもどちらを選ぶか決めかねているというなら、ぜひ一度オープンキャンパスに参加して、実際の授業を体験してみましょう!
「総合学園ヒューマンアカデミー」では、システムエンジニアやアプリ制作、AIエンジニアなどに必要なスキルを着実に身に着けられる「ITカレッジ」を始めとするさまざまなコースが用意されています。ヒューマンアカデミーならオンラインでの受講も可能なので、自分に合った方法を見つけてみてくださいね。
資料請求:https://www.athuman.com/sysform/ha-shiryou-sp/
学校見学:https://www.athuman.com/sysform/ha-kengaku-sp/
体験授業(オープンキャンパス):https://ha.athuman.com/trial-class/