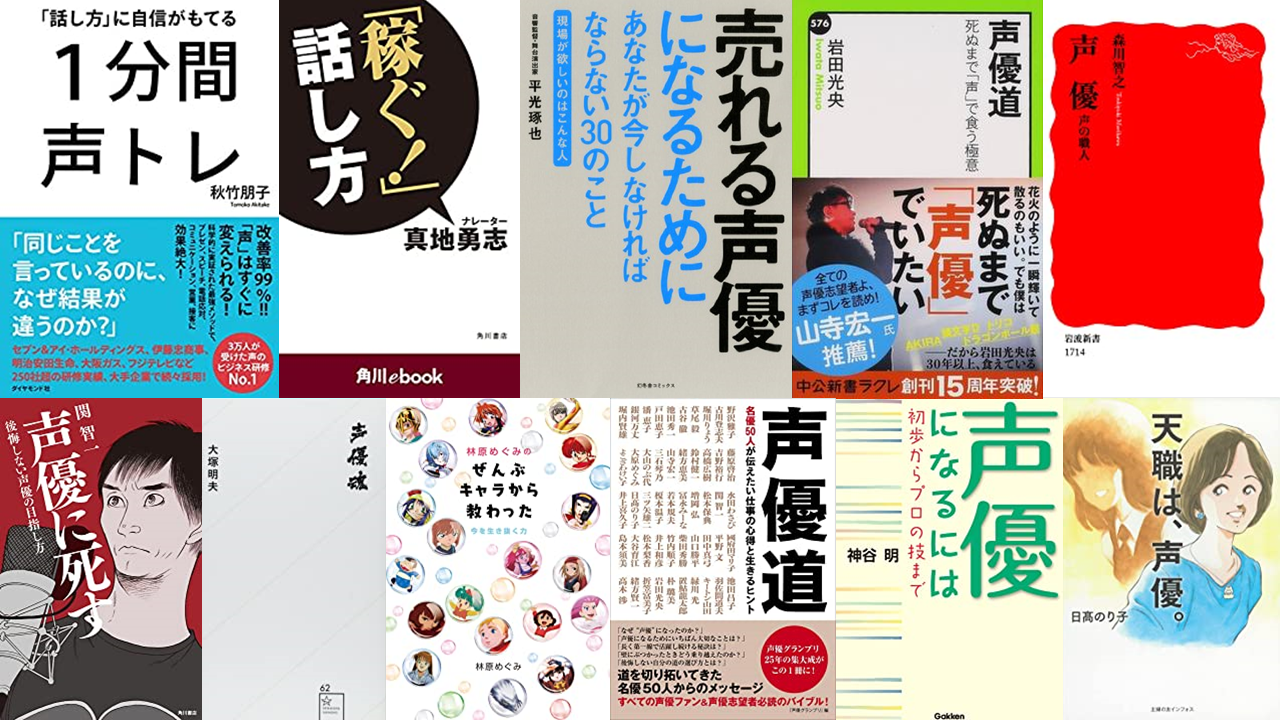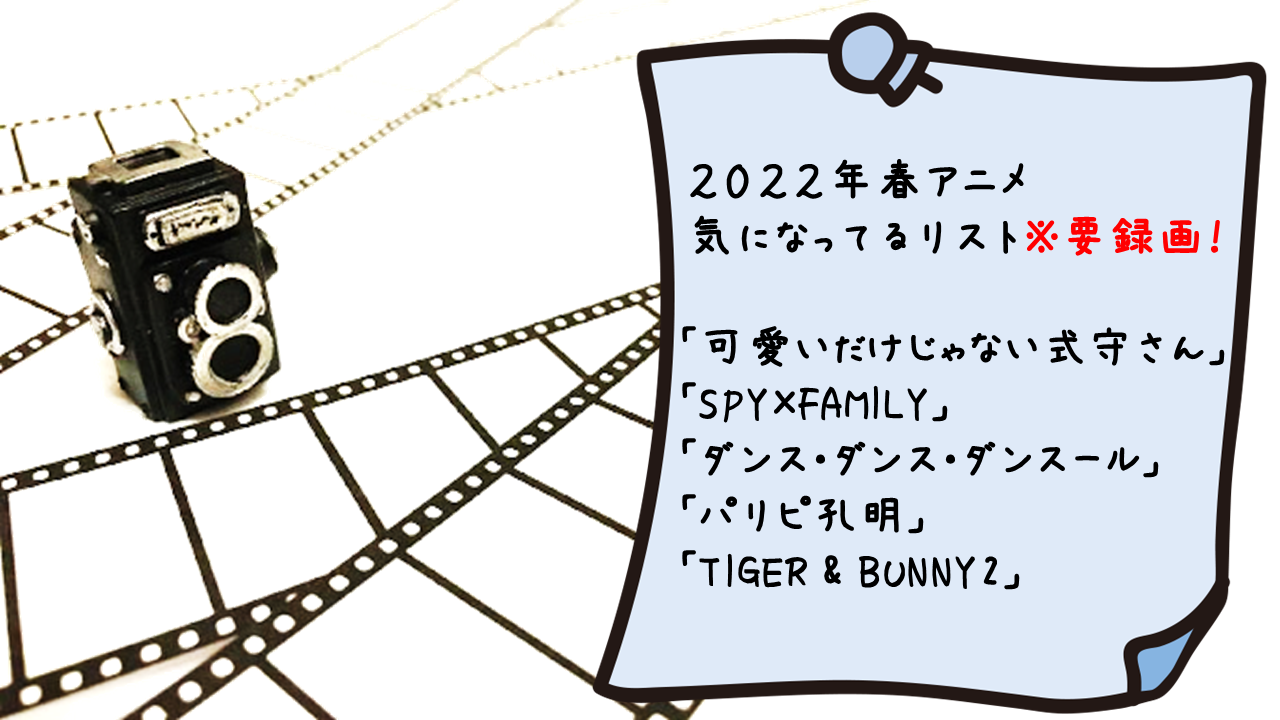e-Sports
eスポーツ事業のビジネスモデルを紹介!市場規模や参入企業の例も解説
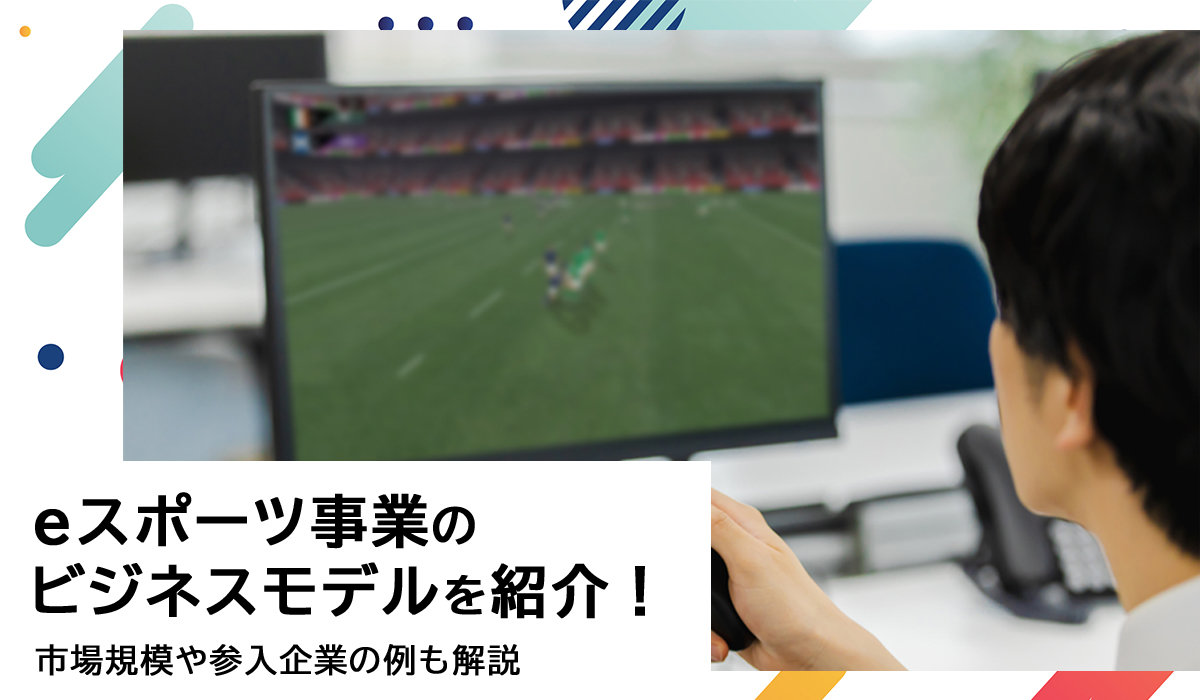
eスポーツは、世界的に市場規模が拡大している分野です。そのため、プレイヤーと運営者、両方の視点で見ても多くのビジネスチャンスが眠っています。詳しいビジネスモデルはプレイヤーと運営者のそれぞれで異なり、プレイヤーなら「大会の賞金で稼ぐ」、運営者なら「チームや施設の運営に関わる」などが代表的です。
どのビジネスモデルを選ぶかによって、具体的なゲームとの関わり方や必要なスキルなどは異なります。そのため、自分の希望や性格を踏まえたうえで、将来のルートを選ぶことが大切です。
本記事では、eスポーツ事業のビジネスモデルや市場規模、参入企業の例を紹介します。
eスポーツの市場規模は世界的に成長している
eスポーツの市場規模は「世界・日本」の両方において成長を続けています。
世界の市場規模は、角川アスキー総合研究所のレポートによると、2025年に「約18億6,620万ドル」まで到達すると見込まれています(2022年時点の予測)。
日本の市場規模は、一般社団法人日本eスポーツ連合の「日本eスポーツ白書2023」によると、2022年の実測値で「約126億円」に到達しました。実際、日清食品ホールディングス株式会社や株式会社ローソン、KDDI株式会社など、大手企業がeスポーツ事業に続々と参入しています。
このように、eスポーツの需要は今後も伸びると予測されており、「将来仕事で関わりたい」と考える人にとってチャンスといえるでしょう。
「どんな形でeスポーツに関わりたいか?」を考えて進路を決めよう
ビジネスでeスポーツに関わるルートとしては、大きく「プレイヤー」と「運営」の2つがあります。いずれのビジネスモデルも、以下のように細かく分類できます。
| プレイヤー | ・大会の賞金で稼ぐ ・スポンサーにサポートしてもらう ・動画配信で収入を得る |
| 運営 | ・eスポーツチームの運営に携わる ・eスポーツ大会の開催に携わる ・eスポーツ体験施設の運営に携わる ・eスポーツ事業へ参入している企業に就職する |
【プレイヤー視点】eスポーツ業界の主なビジネスモデル

「プレイヤー視点」で見たeスポーツ業界の主なビジネスモデルは、以下の3つです。
- 大会の賞金で稼ぐ
- スポンサーにサポートしてもらう
- 動画配信で収入を得る
大会で賞金を獲得する
プレイヤーとしてオーソドックスなビジネスモデルが、「大会に出場して賞金を獲得する」というものです。純粋なゲーム好きからすると、最も理想的な関わり方でしょう。
以下のように賞金額が大きい大会もあるため、実力があれば大幅な収入アップを狙えます。
- The International 2024:260万ドル(デンマーク)
- 2024 League of Legends World Championship:222万5,000ドル(ヨーロッパ各地)
- Intel Extreme Masters RIO 2024:25万ドル(リオデジャネイロ)
- RAGE SHADOWVERSE 2024 SUMMER:1,000万円(日本)
- モンストグランプリ2024:1,500万円(日本)
eスポーツの大会で扱うゲームには、League of Legendsやシャドウバース、Dota 2など、さまざまな種類があります。そのため、自分の得意分野や好きなジャンルなどを考慮してゲームを決めるとよいでしょう。
eスポーツの具体的な種目は、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:eスポーツの主な種目は10種類!有名なゲームやWorld Cupなどでの採用種目も解説
スポンサーにサポートしてもらう
有名なプレイヤーであれば、以下のような形でスポンサーからサポートが受けられます。
- 企業ロゴが入ったユニフォームを着て広告収入を得る
- 大会までの交通費や宿泊費を負担してもらう
- eスポーツに必要な機器を提供してもらう
- チームとして協賛金を得る
スポンサーは広告効果を見込んでプレイヤーやチームを支援します。そのため、大会の結果が悪かったりSNSでの影響力が下がったりすれば、契約を打ち切られることもあるでしょう。一方で、成果さえ残せれば、長期的に資金や機器をサポートしてもらえる点が魅力的です。
動画配信で収入を得る
有名なプレイヤーであれば、主に「YouTube・ニコニコ生放送などで配信映像を流して広告収入を得る」「ライブ配信を行い、リアルタイムで投げ銭を得る」といった方法で収入を獲得できます。視聴者から直接課金してもらうスタイルのため、「SNS上でコミュニケーションを取る」「配信のトークでファンを楽しませる」など、ゲームの腕前以外の面でスキルアップが必要です。
【運営者視点】eスポーツ業界の主なビジネスモデル

「運営者視点」で見たeスポーツ業界の主なビジネスモデルは、以下の4つです。
- eスポーツチームの運営に携わる
- eスポーツ大会の開催に携わる
- eスポーツ体験施設の運営に携わる
- eスポーツ事業へ参入している企業に就職する
eスポーツチームの運営に携わる
eスポーツチームの運営を通じて、プレイヤーの教育に携わるという選択肢もあります。プレイヤー経験を持つ人であれば、より現場目線で適切なアドバイスができます。現役時代に取り組んでいたゲームであれば、自分の知見や経験を存分に伝えられるため、アドバイスを受けるプレイヤーも心強いはずです。
とくにeスポーツは、20代後半で引退する人も珍しくありません。そのため、eスポーツチームの運営も含め、自分の経験を活かせるセカンドキャリアについて早めに考えることが重要です。
eスポーツ大会の開催に携わる
eスポーツの大会を開催することで、以下のようにさまざまな方法で利益を獲得できます。
- スポンサー収入
- 現地およびオンラインの観戦チケット収入
- グッズ収入
- 放映権料
- 会場で出店している飲食店からの収入
とくにアメリカでは、市場の売上の「58%」がスポンサー収入で成り立っており(2020年時点)、eスポーツ業界を支える重要な柱であることがわかります。
大会を開催する場合は、集客に向けたプロモーション戦略を設計したり本番までのスケジュールを管理したりできるビジネススキルが必須です。
eスポーツ体験施設の運営に携わる
eスポーツ体験施設の運営に携わることもおすすめです。自分が好きなゲームをプレイできる施設の運営に携わることができれば、仕事へのモチベーションも高まります。
以下のように自治体や大手企業が運営している施設など、さまざまな種類があるため、自分が好きなゲームなどを踏まえて選ぶとよいでしょう。
- RED° TOKYO TOWER:eモータースポーツや謎解き、ボードゲームなど多様なエンタメが体験できる
- REDEE:eモータースポーツや没入型VRなどのデジタルコンテンツが体験できる
- eスポーツスポット大東:大阪府大東市が運営している
- eSPORTS CAFE AIM:ゲームセンター感覚でさまざまなeスポーツを楽しめる
- Café&Bar RAGE ST:カフェ&バーエリアで食事も楽しめる
- KEIO eSPORTS LAB.:京王電鉄がeスポーツを活用したスクール施設をプロデュースしている
- esports Challenger's Park:配信エリア、グッズショップ、カフェ、観戦ルームなどが集まっている
eスポーツ事業へ参入している企業に就職する
eスポーツ事業に参入している企業へ新卒で就職することもひとつの手です。企業の参入形態としては、主に以下が挙げられます。
- eスポーツ大会へ協賛し、機器や賞金を提供する
- eスポーツチームを運営する
- eスポーツ関連製品を販売する
自分の理想に近い事業を行う企業に就職できれば、安定した収入を受け取りながら好きなゲームに携われます。
eスポーツ事業に参入している企業の一例
それでは具体的に、eスポーツ事業へ参入している企業の一例をチェックしましょう。新卒で就職先を考える際の参考にしてください。
- 株式会社Cygames
- 再春館システム株式会社
- 日清食品株式会社
- 日本コカ・コーラ株式会社
- 株式会社テクリオ
株式会社Cygames
株式会社Cygamesは、モバイルゲームや漫画、アニメなど、エンターテインメントに関わる事業を手広く運営している企業です。eスポーツ事業では、以下のように幅広い種類のビジネスを展開しています。
- 「Shadowverse World Grand Prix」「GBVS Cygames Cup」といった大会の開催
- プレイヤーの引退後を支援する「セカンドキャリア支援プログラム」の運営
- リアルカードゲーム「Shadowverse EVOLVE」の大会の開催
- 企業や自治体が開催するeスポーツイベントへの協賛
大会の開催から引退したプレイヤーの支援まで、幅広い観点からeスポーツを支えている企業です。
再春館システム株式会社
再春館システム株式会社は、ドモホルンリンクルで知られる再春館製薬所のグループ企業です。通販サイトを運営する企業へのアドバイスやスマホアプリの開発などを行っています。
再春館システム株式会社は、「Saishunkan Sol 熊本」というeスポーツチームを運営しています。日本初のプロゲーマーであるウメハラ選手やふ~ど選手など、有名なeスポーツプレイヤーが在籍している点が特徴です。さらに、プロプレイヤーの輩出を目的にした「SS熊本アカデミープロジェクト」も行っており、次世代の育成も積極的に行っています。
参照:再春館システム株式会社 | SaishunkanSol熊本ウメハラ選手ふ~ど選手加入
日清食品株式会社
日清食品株式会社は、カップヌードルやチキンラーメン、日清のどん兵衛など、多数の国民的商品を生み出している企業です。
eスポーツ事業では、韓国のeスポーツチーム「DRX」への協賛を行っています。さらに、ゲーマー向け食品「日清ゲーミングカップヌードル エナジーガーリック&黒胡椒焼そば」を発売するなど、ユニークな形でeスポーツ事業に参入している点が特徴です。
参照:
VALORANT4JP |「DRX」が「日清食品」とスポンサー契約締結を発表
日清食品グループ | 新発売のお知らせ
日本コカ・コーラ株式会社
日本コカ・コーラ株式会社は、コカ・コーラやい・ろ・は・す、綾鷹、アクエリアスなど、有名な飲料品を多数抱える企業です。eスポーツ事業では、高校生向けeスポーツ大会「STAGE:0(ステージゼロ)」のトップスポンサーを務めています。第7回大会は、2025年の大阪・関西万博で開催されることが決まっています(2024年10月時点)。
株式会社テクリオ
株式会社テクリオは、就労継続支援サービスを提供している企業です。就労継続支援サービスとは、障がいや病気の影響で一般企業での勤務が難しい人に向けて、働く場所を提供する施設のことです。
eスポーツ事業では、全国の障がい者施設が参加する大会の運営や、JeSU公認プロeFootballプレイヤーであるGENKIモリタ選手の活動サポートなどを行っています。
参照:
株式会社テクリオ
全国障がい者施設対抗 「ぷよぷよeスポーツ」大会 選抜戦 in テクリオ
PR TIMES | 初ストリートeスポーツ:関西サッカーフェスにも登場
総合学園ヒューマンアカデミーなら幅広いビジネスモデルへの対応力を身に付けられる!
このように、eスポーツには「プレイヤー」「運営」のそれぞれで多くのビジネスモデルがあります。さまざまな関わり方があるため、「スキルを磨いて長くプレイヤーとして活躍したい」「eスポーツ事業に参入している企業に就職して業界に大きく貢献したい」など、自分の希望を踏まえて進路を決めることが大切です。
もちろん、中には「eスポーツを仕事にしたいが将来の関わり方はまだわからない」という人もいるでしょう。その場合は、eスポーツを仕事にするうえで必要なスキルが勉強できる「総合学園ヒューマンアカデミー」へお越しください。
総合学園ヒューマンアカデミーの「e-Sportsカレッジ」では、以下2つの専攻から学びたいコースを選べます。
- プロプレイヤー専攻
- e-Sportsビジネス専攻
プロプレイヤー専攻では「プレイヤー視点のスキル」、e-Sportsビジネス専攻では「運営者視点のスキル」が勉強できます。そのため、将来的にどんなビジネスモデルを選んでも、対応できる力が身に付くでしょう。
プロプレイヤー専攻
プロプレイヤー専攻では、現役のプロプレイヤーから、プロの考え方やプレイ技術、戦略などが学べます。総合学園ヒューマンアカデミー自身もプロチームの「Human academy CREST GAMING」を抱えており、在学中にスキルアップしてトライアウトに合格できれば、下部組織の「CREST GAMAING アカデミー」に所属可能です。
さらに、動画編集スキルや配信時に必要なフリートークスキルなども指導してもらえるため、プレイヤー引退後のキャリアも見据えて長期的にレベルアップできます。
e-Sportsビジネス専攻
e-Sportsビジネス専攻では、eスポーツ大会の開催やゲームイベントの企画、チーム運営など、プレイヤー以外の道でeスポーツ業界に関わるために必要なスキルが学べます。在学中に実際の大会企画から当日運営までを体験できるため、実践的なビジネススキルが身に付くでしょう。
また、海外チームと協力し、eスポーツをビジネスの視点で研究する体制が整っていることも特徴です。そのため、業界の最先端の情報をキャッチし、世間の流れに合わせて対応できるスキルを得ることもできます。
このように、総合学園ヒューマンアカデミーには、eスポーツ業界で必要なスキルをさまざまな角度で学べる環境が整っています。「eスポーツビジネスに興味がある」という人は、まず以下のページから資料だけでもご覧ください。